2025.08.12
【比較表】カスタマーサポートとコールセンターの違いはなに?4つの観点から解説
CSブログ
「上司に『カスタマーサポートとコールセンターの違い』をうまく説明できない…」
「うちの部署は、結局どちらを目指すべきなんだろう?」こんな疑問や悩みを抱えていませんか?
多くの企業で混同されがちな、カスタマーサポートとコールセンター。これらは単なる名称の違いではありません。
その定義や役割の違いを正しく理解していないと、自社の顧客対応戦略の方向性を見誤り、最適な体制構築やツール選定に失敗してしまう可能性があります。表面的な知識だけでは、なぜ体制を変える必要があるのか、その投資対効果を上司や関係部署にロジカルに説明することは困難です。
本記事では、以下のような課題を解決します:
- カスタマーサポートとコールセンターの役割やKPIにおける明確な違いの理解
- 自社の顧客対応が現在どのレベルにあるのかを客観的に評価する方法
- リソースが限られていても実践可能な、現実的な体制移行ステップの把握
- 上司や関係者を納得させるための、データに基づいた具体的な説明ロジックの習得
この記事では上記のような課題を持っている方に向けて、カスタマーサポートとコールセンターの違いから、自社の体制を改革し、企業の成長に貢献するための具体的なステップまでを詳しく解説します。この記事を読めば、もう用語の定義に迷うことはありません。自信を持って自社の顧客対応戦略を語り、変革の第一歩を踏み出せるようになります。
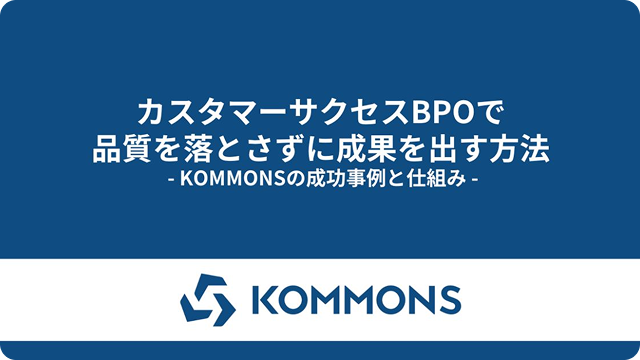
カスタマーサポートとコールセンターの違いを一覧比較
まず結論から言うと、両者の最も大きな違いは「守りのコールセンター、攻めのカスタマーサポート」というスタンスに集約されます。
コールセンターが顧客からの問い合わせ(インバウンド)に効率的に対応する「守り」の役割を担うのに対し、カスタマーサポートは問い合わせ対応に加えて、顧客の成功を能動的に支援し、顧客満足度やLTV(顧客生涯価値)の向上を目指す「攻め」の役割まで担います。
両者の具体的な違いを、以下の比較表で確認してみましょう。
| 比較項目 | コールセンター (守りの顧客対応) |
カスタマーサポート (攻めの顧客対応) |
|---|---|---|
| 役割と目的 | 問い合わせへの受動的な対応と課題解決が主目的。コストセンターと見なされやすい。 | 能動的な支援による顧客の成功(サクセス)が目的。プロフィットセンターを目指す。 |
| 対応チャネル | 電話が中心。 | 電話に加え、メール、チャット、SNSなどマルチチャネルに対応。 |
| 主なKPI | 効率性を重視(応答率、平均処理時間、放棄呼率など)。 | 品質や成果を重視(顧客満足度、NPS®、LTV、解約率など)。 |
| 求められるスキル | 正確な情報提供力、迅速な処理能力、丁寧な言葉遣い。 | 課題解決力に加え、顧客の潜在ニーズを汲み取る傾聴力、アップセル・クロスセルに繋げる提案力。 |
1. 役割と目的の違い:課題解決か、顧客の成功か
コールセンターの主な役割は、顧客からの問い合わせやクレームに迅速かつ正確に対応し、問題を解決することです。
いわば、顧客が抱える「マイナス」を「ゼロ」に戻すことがミッションであり、その性質上、受動的な対応が中心となります。
一方、カスタマーサポートとコールセンターの役割における最も本質的な違いは、その能動性にあります。カスタマーサポートは、問題を解決するだけでなく、顧客が製品やサービスをより効果的に活用し、ビジネス上の成功を収められるように積極的に働きかけます。
これは顧客の「ゼロ」を「プラス」へと引き上げる活動であり、顧客ロイヤルティの向上やLTV(顧客生涯価値)の最大化に直結します。そのため、コストを消費する部門(コストセンター)ではなく、利益を生み出す部門(プロフィットセンター)としての役割が期待されます。
2. 対応チャネルの違い:電話中心か、マルチチャネルか
従来、コールセンターは電話(ボイス)での対応を主としてきました。しかし、顧客のコミュニケーション手段は多様化しています。
メールやWebサイトのフォーム、ビジネスシーンでのチャット、さらにはSNSでの質問など、電話以外の方法で企業と接点を持つことが当たり前になりました。
カスタマーサポートは、このような時代の変化に対応し、電話だけでなく複数のチャネル(マルチチャネル)を統合して顧客対応を行います。近年では、電話とノンボイス(メール、チャット等)の両方に対応する部門を「コンタクトセンター」と呼ぶケースが増えており、これはコールセンターが顧客ニーズの変化に合わせて進化した形態と言えます。
3. 主なKPIの違い:効率性か、顧客ロイヤルティか
役割が違えば、成果を測る指標(KPI)も異なります。コールセンターでは、いかに多くの問い合わせを、いかに速く処理できたかという「効率性」が重視されます。代表的なKPIには以下のようなものがあります。
- 応答率:かかってきた電話にどれだけ対応できたかの割合
- AHT(平均処理時間):1件の問い合わせ対応にかかる平均時間
- 放棄呼率:オペレーターに繋がる前に顧客が電話を切ってしまった割合
対してカスタマーサポートでは、「効率」よりも顧客との関係性の「質」や、それがビジネスに与える「成果」が重視されます。そのため、以下のような顧客視点のKPIが設定されます。
- 顧客満足度(CSAT):個別の対応に対する顧客の満足度
- NPS®(ネット・プロモーター・スコア):企業やブランドへの顧客ロイヤルティ(愛着・信頼)を測る指標
- LTV(顧客生涯価値):一人の顧客が取引期間中にもたらす総利益
- 解約率(チャーンレート):顧客がサービス利用を停止する割合
主要KPI(NPS®, LTV, CES)の測り方と活用ポイント
カスタマーサポートの成果を測る上で重要な3つのKPIについて、もう少し詳しく見てみましょう。
- NPS®(ネット・プロモーター・スコア):「この企業(製品/サービス)を友人や同僚に薦める可能性はどのくらいありますか?」という質問に対し、0~10点で評価してもらい、「推奨者」の割合から「批判者」の割合を引いて算出します。顧客ロイヤルティを数値化し、事業成長との相関が高い指標として注目されています。
- LTV(顧客生涯価値):「平均購買単価 × 購買頻度 × 継続期間」といった計算式で算出され、顧客との長期的な関係性の価値を示します。LTVを高めることは、安定した収益基盤の構築に不可欠です。
- CES(カスタマー・エフォート・スコア):「問題解決のために、どれくらいの労力がかかりましたか?」と質問し、顧客の手間を測る指標です。手間が少ないほど顧客満足度は高まる傾向にあり、顧客体験の改善点を発見するのに役立ちます。
これらの指標を定点観測することで、自社のサポート品質を客観的に評価し、改善に向けた具体的なアクションに繋げることができます。
類似用語(カスタマーサービス、カスタマーセンター)との違い
現場では、さらに類似した用語が使われることがあります。混乱を避けるために整理しておきましょう。
- カスタマーサービスとコールセンターの違い:「カスタマーサービス」は、問い合わせ対応だけでなく、購入前相談や店舗での接客など、顧客と接するあらゆる活動を含む、より広範な概念です。コールセンターは、カスタマーサービスを実現するための機能の一つと位置づけられます。
- カスタマーセンターとサポートセンターの違い:一般的に「カスタマーセンター」は、顧客対応を行う拠点や部門そのもの(物理的な場所や組織)を指すことが多い言葉です。一方で「サポートセンター」は、その機能や役割(特に技術的なサポートなど)を指して使われる傾向があります。ただし、これらの使い分けは企業によって異なり、明確な定義はありません。重要なのは、言葉の定義そのものよりも、自社内で「その部門が何を目的とし、どんな役割を担うのか」を明確に共有することです。
あなたの部署はどっち?自社の顧客対応レベルを診断しよう
ここまで解説した違いを踏まえて、あなたの部署の現状を客観的に評価してみましょう。以下の項目にいくつ当てはまるか、チェックしてみてください。
【現状把握】顧客対応レベル診断チェックリスト
【診断結果】
■ 5個以上当てはまった場合: あなたの部署は「コールセンター」としての役割が強い状態です。まずは現状の業務効率化を進めつつ、どこから付加価値の高い活動を始められるか検討する段階です。
■ 2~4個当てはまった場合: あなたの部署は「カスタマーサポートへの移行期」にあります。既にいくつかの能動的な取り組みを始めている可能性があります。次はその取り組みを仕組み化し、成果を可視化していくフェーズです。
■ 1個以下の場合: あなたの部署は「カスタマーサポート」として機能しています。今後は、さらに顧客データを活用してサービスの改善やLTV向上に貢献し、プロフィットセンターとしての価値を高めていくことが目標となります。
コールセンターから「攻めのカスタマーサポート」へ移行する現実的な3ステップ
「うちも攻めのカスタマーサポートを目指したい。でも、何から手をつければいいのか…」
診断結果を見て、そう感じた方も多いのではないでしょうか。
大掛かりな組織改革や高額なツール導入を想像するかもしれませんが、成功の鍵は「スモールスタート」です。ここでは、限られたリソースでも実践可能な、現実的な3つのステップをご紹介します。
ステップ1:現状の問い合わせ内容を分析し、課題を可視化する
最初に行うべきは、現状の正確な把握です。過去の問い合わせ履歴(電話メモ、メール、応対記録など)を洗い出し、どのような内容が多いのかを分類・集計します。
- よくある質問(FAQ):何度も同じ内容の質問が来ていないか?
- 解決に時間がかかる問題:特定の複雑な問い合わせに多くの時間を取られていないか?
- クレームや不満の声:製品やサービスのどの部分に不満が集中しているか?
勘や経験に頼るのではなく、データを基に「どの業務が最も負担になっているか」「どこを改善すれば最も効果が大きいか」を特定することが、改革の第一歩です。
ステップ2:負担の大きい業務からスモールスタートで効率化する
課題が可視化できたら、最もインパクトの大きい部分から、小さな改善を始めます。いきなり全てを変えようとする必要はありません。
例えば、ステップ1で「同じような操作方法の質問が多い」ことが分かったなら、まずはFAQページを一つ充実させることから始めます。あるいは「簡単な質問で電話が埋まってしまう」のが課題なら、Webサイトに無料のチャットボットを一つ設置するだけでも効果があります。
実際に、出光興産株式会社ではAIチャットボットの導入によってコールセンターへの入電数を約30%削減、株式会社LIFULLではFAQサイトの刷新やチャットボットの活用によって問い合わせ対応の生産性を130%向上させたという成功事例も報告されています。こうした小さな成功体験を積み重ねることが、次のステップに進むための原動力と説得材料になります。
ステップ3:小さな成功体験を基に他部門を巻き込み、体制を拡大する
ステップ2で「FAQを充実させたら、関連する問い合わせが20%減った」といった具体的な成果が出たら、それが次のアクションを起こすための強力な武器になります。そのデータを基に、上司や他部門に協力を仰ぎましょう。
例えば、「問い合わせの中に、営業部門が知るべき製品改善のヒントがたくさんあります」「マーケティング部門と連携して、顧客の声をもとにしたコンテンツを作成しませんか?」といった提案が可能になります。小さな成果をてこにして、徐々に他部門を巻き込み、受動的な問題解決部門から、企業の成長に貢献する能動的なカスタマーサポート部門へと体制を進化させていくのです。
上司や関係者を説得する!説明資料に盛り込むべきポイント
体制改革を進める上で最大の壁となるのが「社内調整」です。特に上司や経営層を説得するには、情熱だけでなく、ロジカルで説得力のある説明が不可欠です。ここでは、あなたの提案が承認されるための説明資料に盛り込むべきポイントを解説します。
1. 「現状の課題」を客観的なデータで示す
「最近、電話が繋がりにくいみたいで…」といった曖昧な問題提起では、相手に危機感は伝わりません。ステップ1で分析したデータを使い、現状を客観的に示しましょう。
- グラフで示す:「応答率がこの半年で15%低下しています」
- 顧客の声を引用する:「SNSで『何度電話しても繋がらない』という不満の声がX件ありました」
- コストを提示する:「同様の問い合わせに、毎月〇〇時間分の人件費(〇〇円相当)が費やされています」
感情論ではなく、誰もが認めざるを得ない「ファクト(事実)」から始めることが重要です。
2. 「目指す姿」と得られるメリットを具体的に語る
課題を示した後は、それを解決した先にある「理想の未来」を提示します。重要なのは、単なる機能改善に留まらず、それが事業全体にどのようなメリットをもたらすかを語ることです。
- コスト削減効果:「チャットボット導入で問い合わせの30%を自動化し、年間〇〇円のコスト削減を見込みます」
- 売上への貢献:「顧客満足度を5%向上させることで、解約率が〇%改善し、LTV(顧客生涯価値)が年間〇〇円向上する見込みです」
- 事業への貢献:「顧客の声を開発部門にフィードバックする仕組みを作り、製品改善のサイクルを速めます」
これにより、顧客対応部門が単なる「コストセンター」ではなく、企業の利益に貢献する「プロフィットセンター」へと変わる可能性を示すことができます。
3. よくある反論への切り返しトーク例
提案の際には、必ずと言っていいほど反論や懸念が示されます。あらかじめ想定される反論への回答を準備しておくことで、自信を持って議論に臨むことができます。
想定される反論①:「結局、コストが増えるだけじゃないか?」
切り返しトーク例:
「おっしゃる通り、初期投資はかかります。しかし、こちらの資料をご覧ください。この投資によって、まず単純な問い合わせ対応にかかる人件費が年間〇〇円削減できます。さらに、その削減できたリソースを、既存顧客のフォローに充てることで、解約率が〇%改善し、結果として年間〇〇円の収益増が見込めます。短期的なコストではなく、長期的な投資対効果(ROI)でご判断いただければと思います。」
想定される反論②:「今のままでも、なんとかなっているじゃないか。」
切り返しトーク例:
「はい、現場の努力でなんとか回っているのが現状です。しかし、こちらのデータが示す通り、顧客満足度は緩やかに低下しており、これは将来の解約率上昇のサインとも言えます。競合他社がチャットサポートなどを導入し顧客体験を向上させている中、現状維持は、実質的には市場から後退していることと同じです。顧客が離れてから対策するのでは手遅れになります。今こそ、将来のための布石を打つべきだと考えます。」
まとめ:顧客対応を企業の成長エンジンに変えよう
本記事では、カスタマーサポートとコールセンターの違いを軸に、自社の顧客対応を進化させるための具体的なステップと、社内を説得するためのポイントを解説しました。
両者の違いは、単なる言葉の定義や機能の違いではありません。それは、顧客とどう向き合い、顧客対応部門を企業の資産としてどう位置づけるかという「思想」の違いです。受動的に問題を処理するだけの部門から、能動的に顧客を成功に導き、企業の利益に貢献する部門へ。
この記事で得た知識とフレームワークが、あなたの部署の変革を後押しし、あなた自身がその中心的な役割を担うための武器となれば幸いです。まずは自社の現状を分析する小さな一歩から、顧客対応を企業の成長エンジンへと変える旅を始めてみましょう。