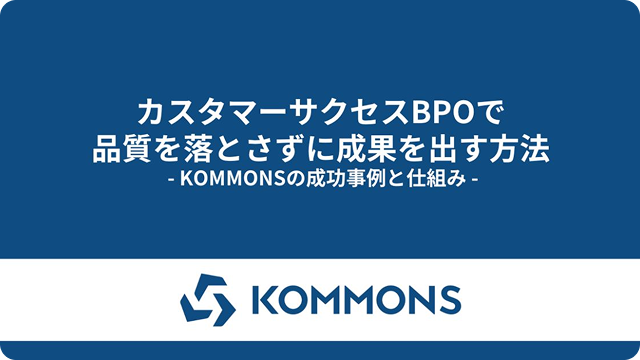2025.05.01
カスタマーサクセスにおけるリテンションとは?売上安定のカギとなる重要性と基本知識を解説
CSブログ
「顧客の継続率(リテンション)が思うように伸びない」
「解約(チャーン)が増えてきて、LTVがなかなか上がらない」
サブスクリプションビジネスが主流となる中、多くの企業がこうした悩みを抱えています。
顧客にいかにサービスを長く使い続けてもらうか、すなわち「リテンション」の向上は、事業成長の生命線と言っても過言ではありません。
この記事では、カスタマーサクセスにおけるリテンションの重要性から、具体的な施策、成功のためのポイントまで、あなたの疑問や課題を解決するために網羅的に解説します。リテンション率を高め、安定した収益基盤を築くためのヒントがきっと見つかるはずです。
カスタマーサクセスにおけるリテンションとは?
まず、「リテンション」という言葉の基本的な意味と、なぜそれがカスタマーサクセスにおいて非常に重要視されるのか?理由についてご紹介します。
リテンションの定義は、顧客を「維持」すること
リテンション(Retention)とは、英語で「維持」「保持」を意味する言葉です。ビジネス、特にカスタマーサクセスの文脈においては、「既存顧客との関係性を維持し、サービスや製品を継続的に利用してもらうこと」あるいはそのための活動全般を指します。
特に、月額課金や年額課金といったサブスクリプションモデルのビジネスでは、顧客が契約を更新し続けることが売上の安定と成長に直結するため、リテンションは極めて重要な概念となります。
単に「解約させない」という守りの視点だけでなく、顧客満足度を高め、より長期的な関係性を築くことで、LTV(顧客生涯価値)を最大化していく攻めの側面も持ち合わせています。
カスタマーサクセスにおけるリテンションの位置づけ
カスタマーサクセスは、「顧客の成功」を能動的に支援することで、顧客のリテンションを高め、LTVを最大化することをミッションとしています。
従来のカスタマーサポートが受動的な問題解決(クレーム対応など)が中心だったのに対し、カスタマーサクセスは、顧客がサービスを最大限に活用し、期待する成果(成功)を得られるように、先回りして働きかけます。
この「顧客の成功」こそが、結果的にリテンション、すなわち顧客の継続利用意向を高める最も重要なドライバーとなるのです。したがって、リテンション向上は、カスタマーサクセス活動の根幹をなす目標の一つと言えます。
「維持」だけではない、攻めのリテンション戦略
リテンションというと、「解約を防ぐ」という守りのイメージが強いかもしれません。しかし、真にLTVを最大化するためには、「維持」に加えて「拡大」の視点を持つことが重要です。
つまり、顧客満足度を高めた上で、アップセル(より上位のプランへの移行)やクロスセル(関連する別サービスの利用)を促進していく「攻め」のリテンション戦略です。カスタマーサクセスは、単なる顧客維持部門ではなく、企業の新たな収益ドライバーとなり得るポテンシャルを秘めているのです。
カスタマーサクセスにおいてリテンションが重要な4つの理由
リテンションが重要視される理由はいくつかあります。特に現代のビジネス環境において、その重要性は増すばかりです。
1. 安定した収益基盤の構築ができ、LTV(顧客生涯価値)の最大化に繋がるから
既存顧客からの継続的な収益は、ビジネスの安定性を大きく左右します。新規顧客の獲得には波がありますが、高いリテンション率を維持できれば、予測可能な収益基盤を築くことができます。
顧客が長くサービスを利用し続ければ、それだけ企業にもたらす総利益(LTV)は大きくなります。リテンション施策は、このLTVを最大化するための最も効果的な手段の一つです。
2. 新規顧客獲得コストと比べ、既存顧客の維持コストが低いから(1:5の法則)
一般的に、新規顧客を獲得するコストは、既存顧客を維持するコストの5倍かかると言われています(1:5の法則)。サブスクリプション型ビジネスにおいて、リテンションに注力することは、販促/販管費用を押し下げ・事業全体の利益率を高める上でも非常に重要です。
また、顧客との信頼関係を十分に構築することで、エクスパンションによる顧客単価の引き上げにも繋がります。
3. 顧客ロイヤルティの向上による好循環が起こるから
リテンション施策を通じて顧客満足度が高まると、顧客は単なる利用者から、サービスを推奨してくれる「ファン」へと変化していく可能性があります。満足した顧客からの口コミや紹介は、新たな顧客獲得にも繋がります。
とりわけBtoC、あるいはBtoB/C型モデルのサブスクリプションビジネスでは、顧客の母集団が多いためバイラルマーケティングの再現性が高く、リテンションへの注力がより肯定されます。
4. 競争優位性の確立に繋がるから
他社サービスへの乗り換えが容易になっている現代において、高いリテンション率は顧客が自社サービスに価値を感じ、満足している証拠です。これは強力な競争優位性となります。
高いリテンションレートが競合優位性に繋がる理由
高いリテンションレートを保持すること、つまり事業のLTVが高い状態を保持することは、2つの観点から競合優位性の確立に繋がります。
1つはマーケティングにおける限界CPAコストの観点です。LTVが高い事業は販促費を高く設定しても収益性を維持したまま運営できるので、競合他社よりも長期にわたって高額の広告費を投下することが肯定されます。
2つ目はクロスセルの観点です。主軸となるビジネスのリテンションレートが高ければ、顧客に対する新たな課題解決の機会が生まれやすくなります。よって、競合企業に対して相対的に価値提供と売上創出の白地が多くなります。
リテンション率の計算方法と目標設定の考え方
リテンションの重要性を理解したところで、次にそれを測るための指標である「リテンション率」について見ていきましょう。リテンション率を正しく計算し、適切に目標設定することが、効果的な施策実行の第一歩です。
リテンション率の基本的な計算式
リテンション率とは、特定の期間において、サービスや製品の利用を継続した顧客の割合を示す指標です。カスタマーサクセスの成果を測る上で、最も基本的なKPI(重要業績評価指標)の一つとなります。
基本的な計算式は以下の通りです。
リテンション率(%) = (期間終了時の顧客数 - 期間中の新規顧客数) ÷ 期間開始時の顧客数 × 100
例えば、月初に1000人の顧客がいて、月末に1100人になったとします。その月に新たに獲得した顧客が200人だった場合、
(1100人 – 200人) ÷ 1000人 × 100 = 90%
となり、この月のリテンション率は90%となります。
計算する期間(月次、四半期、年次など)は、ビジネスモデルや分析の目的に応じて設定します。
リテンション率とチャーン率の関係
リテンション率と密接に関係する指標に「チャーンレート(解約率)」があります。チャーンレートは、特定の期間内にサービスを解約した顧客の割合を示す指標です。
- チャーン率:「どれだけ顧客を失っているか」をダイレクトに示す。改善余地の大小感がひと目でわかる。
- リテンション率:「残存顧客の生存」を示す。長期的なファンづくりやLTV(顧客生涯価値)の向上施策の効果測定に直結。
多くの場合、リテンション率 + チャーン率 = 100% の関係になります(※計算方法の定義によっては厳密に一致しない場合もあります)。
つまり、リテンション率を高めることは、チャーン率を下げることと表裏一体です。どちらの指標を重視するかは企業の方針によりますが、両方をセットで見ていくことで、顧客の動向をより深く理解することができます。
リテンション率とチャーン率を同時に見ていく意義
細かい言及は避けますが、一般的にチャーン率は「今月どれだけ顧客を失ったのか」を鋭くキャッチするためにモニタリングします。
一方でリテンション率は「累積的にどれだけの顧客が残り続けているのか」を長期的にモニタリングしていく指標として扱われます。
リテンション率を見ることで、例えば「利用3ヶ月目の解約は20%だが、利用10ヶ月目の解約は8%である」といった事実を収集することができます。
これにより、”利用継続が解約抑制に有効” という示唆を出すことができ、3ヶ月目のオンボーディング改善が課題 と判断できるようになります。
詳しくはこちらの記事が非常に勉強になります!ぜひ一読ください。
確率モデルで解き明かすリテンションレートとチャーンレートの本質(note:岩田健吾)
カスタマーサクセスでリテンションを高める具体的な施策
リテンションの重要性と計測方法を理解した上で、いよいよ具体的な施策について見ていきましょう。ここでは、カスタマーサクセスが主体となって実行できる、効果的なリテンション向上策をいくつかご紹介します。
1. オンボーディングの最適化
顧客がサービスを契約した後、最初に価値を実感し、基本的な操作をスムーズに習得できるように支援するプロセスが「オンボーディング」です。この初期体験がうまくいかないと、顧客はサービスを使いこなせないまま早期に離脱してしまう可能性が高まります。
具体的な施策例:
- ウェルカムメールや導入ガイダンスの送付
- 初期設定のサポート(個別説明会、チュートリアル動画、FAQ)
- サービス活用目標の設定支援
- 導入初期の利用状況モニタリングとフォローアップ
オンボーディングの質を高めることは、リテンションの土台を築く上で最も重要と言っても過言ではありません。
2. ヘルススコアの活用
ヘルススコアとは、顧客がサービスを健全に(=継続利用の可能性高く)利用しているかどうかを測るための指標です。サービスの利用頻度、特定機能の利用率、サポートへの問い合わせ回数、アンケート結果などを組み合わせてスコアリングします。
ヘルススコアを定期的にモニタリングすることで、解約リスクの高い顧客(スコアが低い顧客)を早期に発見し、プロアクティブ(先回り)な対応をとることが可能になります。これによって「解約(チャーン)の予兆や原因をリアルタイムで把握できない」「『辞めたい』と言われる前に予兆をキャッチ・先回りしたい」などといった課題を解決できます
具体的な施策例:
- ヘルススコア定義の明確化と算出ロジックの構築
- スコアに応じたアラート設定と担当者への通知
- スコア低下顧客へのヒアリングやサポート提供
- スコア良好顧客へのアップセル・クロスセル提案
3. タッチモデル(ハイタッチ・ロータッチ・テックタッチ)の使い分け
全ての顧客に同じように手厚いサポートを提供するのは、リソース的に困難です。そこで、顧客のLTVや状況に応じて、アプローチの仕方を変える「タッチモデル」の考え方が重要になります。
タッチモデルの分類:
- ハイタッチ: LTVが高い大口顧客などに対し、専任担当者が個別にて手厚いサポートを提供する。(例:定期的なミーティング、個別コンサルティング)
- ロータッチ: 中程度のLTVの顧客に対し、セミナーやワークショップ、限定的な個別サポートなどを組み合わせて支援する。
- テックタッチ: LTVが低い、あるいは顧客数が多い場合に、テクノロジーを活用して効率的にサポートを提供する。(例:FAQ、チュートリアル動画、ステップメール、チャットボット)
限られたリソースを最適配分し、効果的・効率的にサクセス活動を回すために、自社の顧客ポートフォリオに合わせてタッチモデルを設計・運用することが求められます。これは「リソース最適配分で効果的・効率的にサクセス活動を回したい」「人的・時間的リソースが足りず、対応が後手になりがち」という課題への対応策となります。
4. アップセル・クロスセルの促進
「攻め」のリテンションとして、アップセル(上位プランへの移行)やクロスセル(関連サービスの追加購入)を促進することも重要です。これは、顧客が現在のサービスに満足し、さらなる価値を求めているサインでもあります。
ただし、無理な売り込みは逆効果になるため、あくまで顧客の成功や課題解決に繋がる提案であることが前提です。ヘルススコアや利用状況データを分析し、適切なタイミングと顧客に対して提案を行うことが成功の鍵となります。
アップセル・クロスセルが成功すれば、顧客単価が向上し、結果的にLTVの最大化、さらにはネガティブチャーン抑制の達成に繋がります。
5. フィードバック収集とサービス改善
顧客がなぜ継続し、あるいはなぜ解約するのか、その理由を最もよく知っているのは顧客自身です。アンケート調査、インタビュー、ユーザーコミュニティでの発言、サポートへの問い合わせ内容など、あらゆるチャネルを通じて顧客からのフィードバック(声)を積極的に収集し、分析することが重要です。
集めたフィードバックは、単に収集するだけでなく、サービス改善や新機能開発、サポート体制の見直しなどに活かしていく必要があります。これにより、顧客満足度を高め、リテンション向上に繋げることができます。
部門連携なくしてリテンション向上なし
ここまで様々な施策を紹介しましたが、これらの多くはカスタマーサクセス部門だけで完結するものではありません。例えば、オンボーディングの質はプロダクトの使いやすさにも依存しますし、顧客からのフィードバックはプロダクト開発部門や営業部門にも共有されるべきです。
真のリテンション向上を実現するためには、部門間の壁を取り払い、顧客情報を共有し、連携して顧客の成功を支援する体制(The Modelのような考え方)を構築することが不可欠です。経営層を巻き込み、全社的な取り組みとして推進していく視点が求められます。
リテンション施策を進める上での注意点と成功のコツ
リテンション向上のための施策を実行する際には、いくつか注意すべき点や、成功確率を高めるためのコツがあります。これらを意識することで、より効果的に施策を進めることができるでしょう。
データドリブンな意思決定の重要性
勘や経験だけに頼るのではなく、顧客データ(利用状況、ヘルススコア、フィードバックなど)に基づいて施策を立案し、効果を測定・改善していく「データドリブン」なアプローチが不可欠です。
「データや数値はあるが、具体的な打ち手を決められない」「データは揃っているのに動けず、機会損失が積み重なること」といった悩みは、まさにデータ活用の課題を示しています。データを収集・分析するだけでなく、そこからインサイト(示唆)を抽出し、具体的なアクションプランに落とし込むスキルが求められます。
どの施策がリテンション率向上に寄与しているのかを定量的に評価し、効果の高い施策にリソースを集中させることが重要です。PDCA(計画・実行・評価・改善)サイクルを回し、継続的に施策を最適化していきましょう。
ツール導入の落とし穴と活用のポイント
近年、カスタマーサクセス活動を支援するためのツール(リテンションテック、サクセスツール)が数多く登場しています。これらのツールは、ヘルススコアの算出、コミュニケーションの自動化、データ分析などを効率化する上で非常に有効です。
しかし、マーケティングリサーチのインサイトにもあるように、「ツールを導入しても魔法の杖にならず、運用・仕組み化が本丸」であることを見落としてはいけません。ツールはあくまで手段であり、導入することが目的ではありません。
自社の課題や目的に合ったツールを選定し、導入後の運用体制や活用ルールをしっかりと整備することが重要です。ツールに振り回されるのではなく、ツールを使いこなして成果に繋げる意識を持ちましょう。
属人化を防ぎ、組織で取り組む体制づくり
カスタマーサクセス活動が特定の担当者のスキルや経験に依存してしまう「属人化」は、多くの組織が抱える課題です。ノウハウが共有されず、担当者が変わると対応品質が低下したり、施策が継続できなくなったりするリスクがあります。
これを防ぐためには、成功事例やノウハウをドキュメント化し、チーム内で共有する仕組みを作ることが重要です。また、役割分担や業務プロセスを標準化し、誰が担当しても一定の品質を担保できるような体制を目指しましょう。
「成功体験を作るプロセスが部門や担当者でバラバラ」「ノウハウが属人化し、知見の横展開や標準化が進まない」といった課題は、組織的な取り組みによって解決していく必要があります。
担当者のモチベーション維持と評価設計も忘れずに
カスタマーサクセスは比較的新しい職種であり、「担当者自身もキャリアや評価にまだ不安を持っている」というインサイトがありました。また、「現場で疲弊し、担当者のモチベや離職が進む悪循環」も避けたいペインとして挙げられています。
顧客の成功を支援するカスタマーサクセス担当者自身の「成功」や「働きがい」にも目を向けることが、結果的にリテンション向上に繋がります。担当者の成果を正当に評価する仕組み(リテンション率だけでなく、顧客満足度や貢献度なども考慮)を設計したり、キャリアパスを示したりすることで、モチベーション高く業務に取り組める環境を整えることが、組織全体の成功にとって非常に重要です。
カスタマーサクセスにおけるリテンションまとめ
この記事では、カスタマーサクセスにおけるリテンションの重要性から、リテンション率の考え方、具体的な施策、そして成功のための注意点まで、幅広く解説してきました。
【この記事のポイント】
- リテンションとは: 既存顧客との関係を維持し、継続利用を促すこと
- リテンション率: 顧客維持の状況を測る重要KPI
- 重要施策:
- オンボーディング最適化
- ヘルススコア活用
- タッチモデル設計
- アップセル/クロスセル促進
- フィードバック活用、チャーン分析など
- 成功のコツ:
- データドリブンな意思決定
- ツールの適切な活用
- 属人化防止と組織体制
- 部門連携、担当者のモチベーション維持
表面的な施策に終始するのではなく、顧客の成功体験を深く理解し、データに基づきながらも、顧客一人ひとりと向き合う姿勢が求められます。これはカスタマーサクセス部門だけのミッションではなく、営業、マーケティング、プロダクト開発など、会社全体で取り組むべき重要な経営戦略です。
この記事で得た知識を元に、まずは自社のリテンション状況の分析や、取り組みやすい施策の検討から始めてみてください。