2025.08.12
カスタマーサクセスにおけるハイタッチとは?施策成功のポイントを解説
CSブログ
「重要顧客の解約が続いていて、効果的な対策がわからない…」
「カスタマーサクセスのハイタッチという言葉は聞くけれど、自社でどうやって始めたらいいんだろう?」
「リソースが限られているのに、どこから手をつければいいのか…」
SaaSビジネスの成長に不可欠とされるカスタマーサクセス。その中でも、特に重要な顧客に対して手厚い支援を行う「ハイタッチ」は、解約率の低下やLTV(顧客生涯価値)の最大化に直結する重要な戦略です。しかし、その一方で「コストが高い」「何から始めるべきか計画が立てられない」といった課題から、導入に踏み切れない企業が多いのも事実です。表面的な知識だけでは、自社に最適な形でハイタッチを機能させることはできません。
本記事では、以下のような課題を解決します:
- カスタマーサクセスにおけるハイタッチとは何か、ロータッチとの違いや使い分けの基準がわかる
- コストが高いという懸念を払拭し、投資対効果(ROI)を説明できるようになる
- 限られたリソースを集中させるべき「ハイタッチ対象顧客」を明確に定義できる
- 明日からでも実践できる、具体的なハイタッチ導入の5ステップがわかる
- よくある失敗事例とその回避策を知り、導入の成功確率を高めることができる
この記事では上記のような課題を持っている方に向けて、カスタマーサクセスにおけるハイタッチ戦略の導入から実践までを、失敗しないためのステップに沿って詳しく解説します。
ハイタッチは単なる顧客対応ではなく、LTVを最大化し、事業成長を加速させるための戦略的「投資」です。この記事を参考に、重要顧客との強固なパートナーシップを築く第一歩を踏み出しましょう。
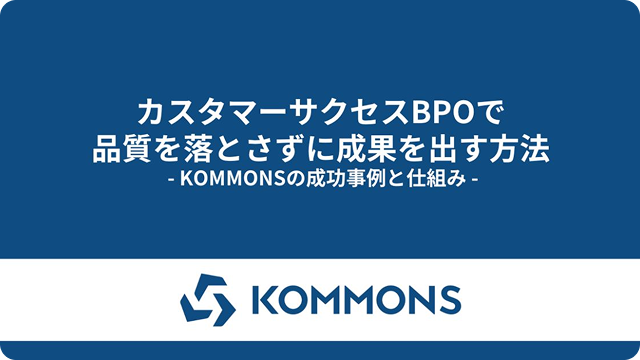
カスタマーサクセスにおけるハイタッチとは?ロータッチとの違いも解説
まず、カスタマーサクセスにおけるハイタッチとは何か、その基本的な定義と、他のアプローチとの違いを理解することが重要です。顧客へのアプローチ方法は、大きく「ハイタッチ」「ロータッチ」「テックタッチ」の3つに分類され、それぞれ対象となる顧客層や目的が異なります。
ここでは、それぞれの特徴と、カスタマーサクセスにおけるハイタッチとロータッチ、テックタッチの違いを明確に解説します。
ハイタッチ:LTV最大化を目指す個別対応
ハイタッチは、LTV(顧客生涯価値)が最も高い最重要顧客セグメントに対して、専任のカスタマーサクセスマネージャー(CSM)が手厚い個別支援を行うアプローチです。
定期的なミーティング、オンボーディング支援、事業課題に対するコンサルティングなどを通じて、顧客との深い信頼関係を構築し、製品・サービスの価値を最大限に引き出すことを目指します。まさに「人の手」をかけた、オーダーメイドの支援と言えるでしょう。
ロータッチ:効率性を重視した部分的・集合的な支援
ロータッチは、ハイタッチとテックタッチの中間に位置するアプローチです。顧客数は多いものの、一社一社に手厚いサポートはできない中間層の顧客を対象とします。
個別の定例会は行わず、複数の顧客を対象としたウェビナーや勉強会、ワークショップなどを開催し、効率的に成功体験を支援します。個別対応が必要な場合は、メールやチャットでのサポートが中心となります。
テックタッチ:テクノロジーを活用した一斉アプローチ
テックタッチは、最も顧客数が多いセグメントに対して、テクノロジーを駆使して一斉にアプローチする手法です。チュートリアル動画、ヘルプセンター、ステップメール、機能アップデートのお知らせなど、人の手を介さずに顧客が自己解決できる仕組みを整備します。
これにより、CSチームはより少ないリソースで多くの顧客をサポートすることが可能になります。
| アプローチ | 対象顧客 | 主な手法 | CSM1人あたりの担当社数(目安) | コスト |
|---|---|---|---|---|
| ハイタッチ | LTVが非常に高い重要顧客 | ・個別の定例会 ・QBR(四半期ビジネスレビュー) ・オンボーディング支援 |
数社〜25社程度 | 高い |
| ロータッチ | LTVが中程度の顧客 | ・集合ウェビナー ・勉強会 ・メール/チャットサポート |
数十社〜数百社 | 中程度 |
| テックタッチ | LTVが比較的低い顧客 | ・ヘルプセンター ・チュートリアル ・ステップメール |
数百社以上 | 低い |
なぜ今ハイタッチが重要なのか?LTV最大化と解約率低下への効果
「ハイタッチはコストがかかる」というイメージから、導入をためらう方も少なくありません。しかし、ハイタッチは単なるコストではなく、事業成長に不可欠な「投資」です。ここでは、ハイタッチがもたらす具体的なビジネスインパクトと、その重要性について解説します。
ハイタッチ戦略がもたらす主な効果は以下の通りです。
- 解約(チャーン)率の低下:手厚い支援によって顧客満足度と製品へのエンゲージメントが高まり、重要顧客の解約を未然に防ぎます。統一された統計はありませんが、多くの成功事例でチャーン抑制効果が報告されています。例えば、ある企業のケーススタディでは、ハイタッチ支援の結果、特定セグメントのチャーンレート(解約率)が5ポイント改善したという報告もあります。
- LTV(顧客生涯価値)の最大化:顧客との強固な信頼関係は、アップセル(上位プランへの移行)やクロスセル(関連製品の購入)の絶好の機会を生み出します。大手コンサルティングファームMcKinseyの報告によると、優れた顧客体験(CX)の変革は、収益を5~10%向上させる可能性があるとされています。解約率の低下と客単価の向上により、LTVは飛躍的に高まります。
- 顧客ロイヤルティの向上と優良なフィードバックの獲得:満足度の高い顧客は、自社の製品やサービスを推奨してくれる強力なエバンジェリスト(伝道師)になります。また、彼らから得られる質の高いフィードバックは、製品開発やサービス改善の貴重なヒントとなります。
ハイタッチにかかる人件費は、これらのリターンを考慮すれば、十分に回収可能な「投資」と捉えることができます。重要なのは、かけたコスト以上の価値を生み出せているかを、ROI(投資対効果)の視点で評価することです。
拡大する国内カスタマーサクセス市場の動向
ハイタッチの重要性は、市場の動向からも見て取れます。株式会社コミューンが発行した「カスタマーサクセス白書2023」によると、調査対象企業の75.2%がカスタマーサクセスの専門部署を設置しており、多くの企業がその重要性を認識し、体制構築を進めていることがわかります。
また、同調査ではCS担当者の年収についても触れられており、「400万円〜600万円未満」が33.3%で最も多く、次いで「600万円〜800万円未満」が25.2%を占めています。これは、専門性が求められる職種として、市場価値が高まっていることの表れと言えるでしょう。こうした市場の活況は、企業が顧客との長期的な関係構築に、より一層投資していく未来を示唆しています。
ハイタッチはどの顧客に適用すべき?失敗しないためのセグメント分け3つの基準
限られたリソースを最大限に活用するためには、「どの顧客にハイタッチを適用するか」という顧客セグメンテーション(分類)が極めて重要です。
すべての顧客に同じ対応をしていては、コストがかさむばかりか、本当に支援が必要な顧客にリソースを集中できません。ここでは、失敗しないためのセグメント分けの具体的な3つの基準を紹介します。
1. 顧客生涯価値(LTV)で判断する
最も基本的で重要な基準がLTVです。LTVとは、一人の顧客が取引期間全体を通じて自社にもたらす利益の総額を指します。一般的に、LTVが高い顧客ほど、手厚いサポートによって解約を防ぐ価値が大きいと言えます。現在の契約プランの金額や、過去の利用実績から将来のLTVを予測し、上位の顧客層をハイタッチの対象候補とします。
これは、売上への貢献度に基づいた、最も分かりやすいセグメント分けの方法です。
2. 製品・サービスの複雑性や潜在価値で判断する
現在の売上だけでなく、将来性も考慮に入れることが重要です。例えば、以下のような顧客はハイタッチの対象となり得ます。
- 製品の活用に支援が必要な顧客:製品の機能が多岐にわたり、使いこなすために専門的なサポートが必要な場合。手厚い支援で活用を促進できれば、将来的に大きな価値を生む可能性があります。
- アップセルやクロスセルの見込みが大きい顧客:現在は小規模な契約でも、事業が急成長しており、将来的に上位プランや関連サービスを利用する可能性が高い顧客。先行投資として関係を構築する価値があります。
3. 企業の戦略的重要性で判断する
売上や潜在価値といった金銭的な指標だけでなく、自社の事業戦略における重要度も判断基準になります。例えば、以下のような顧客です。
- 導入事例としての影響力が大きい顧客:業界で知名度が高い企業や、象徴的なロゴを持つ企業。成功事例として公開できれば、マーケティングや営業活動に絶大な効果をもたらします。
- 特定の業界への足がかりとなる顧客:自社がこれから開拓したいと考えている業界で、最初期の導入企業となった顧客。この顧客を成功させることで、同業界への展開がスムーズになります。
これらの基準を複数組み合わせ、自社の状況に合わせて優先順位をつけ、誰が見ても納得できるセグメントモデルを構築することが成功の鍵です。
ハイタッチ導入で失敗しないための5ステップ
「ハイタッチの重要性や対象顧客はわかった。では、具体的にどう始めればいいのか?」という疑問に答えるため、ここからは明日から実践できる具体的な導入ロードマップを5つのステップに分けて解説します。
ステップ1:目的とKPIを明確にする
まず最初に、「何のためにハイタッチを導入するのか」という目的を明確に定義します。目的が曖昧なままでは、活動が自己満足で終わってしまいます。「重要顧客の満足度を高める」といった抽象的なものではなく、「LTVの最大化」「解約率の低下」など、事業貢献に繋がる具体的な目的を設定しましょう。
次に、その目的を測定可能なKPI(重要業績評価指標)に落とし込みます。例えば、以下のようなKPIが考えられます。
- 解約率(チャーンレート):対象セグメントの解約率を半年でX%改善する。
- 売上継続率(NRR):対象セグメントのNRRを年間でY%向上させる。
- アップセル/クロスセル金額:対象セグメントからのアップセル/クロスセル額を四半期でZ円増やす。
明確なKPIを設定することで、活動の成果を客観的に評価し、ROIを証明する土台を築くことができます。
ステップ2:対象顧客セグメントを定義する
ステップ1で設定した目的とKPIに基づき、前の章で解説した3つの基準(LTV、潜在価値、戦略的重要性)を使って、自社のハイタッチ対象顧客を具体的にリストアップします。ここでは、「重要そうな顧客」といった曖昧な定義ではなく、「ARR(年間経常収益)が〇〇円以上、かつ導入事例化に協力的な顧客」のように、誰が見ても判断できる明確な基準を設けることが重要です。これにより、限られたリソースをどこに集中させるべきかが明確になります。
ステップ3:具体的な支援内容(プレイブック)を作成する
対象顧客が決まったら、彼らを成功に導くための具体的なアクションプランを時系列でまとめた「プレイブック( playbook)」を作成します。プレイブックには、顧客のフェーズ(導入初期、運用定着期など)ごとに、CSMが「いつ」「何を」「どのように」行うかを具体的に記述します。
【プレイブックの記載例】
- オンボーディング期(契約後〜3ヶ月):キックオフミーティングの実施、導入・設定支援、初期トレーニングの提供
- アダプション期(4ヶ月〜):月1回の定例会、活用状況のモニタリングと改善提案、新機能の紹介
- エクスパンション期:QBR(四半期ビジネスレビュー)の実施、成功事例の共有、上位プランや関連製品の提案
プレイブックを作成することで、担当者による対応のバラつきを防ぎ、質の高い支援を標準化・効率化することができます。
ステップ4:体制とリソースを計画する
プレイブックを実行するための体制とリソースを計画します。具体的には、以下の項目を検討します。
- 担当者のアサイン:誰がハイタッチを担当するのかを決定します。
- CSM1人あたりの担当社数:一般的にハイタッチでは1人あたり数社〜25社程度が目安とされていますが、これは製品の複雑性や顧客のARRによって変動します。自社の状況に合わせて現実的な担当社数を設定しましょう。
- 必要なツールや予算:顧客管理のためのCRM/CSツール、Web会議システムなど、活動に必要なツールを洗い出し、予算を確保します。
リソースが不足したまま見切り発車すると、計画が頓挫する原因になります。現実的な実行計画を立てることが重要です。
ステップ5:小さく始めて効果検証と改善を繰り返す
完璧な計画を立ててから始めようとすると、いつまで経っても実行に移せません。重要なのは、小さく始めて、PDCAサイクルを回すことです。いきなり定義した全対象顧客に展開するのではなく、まずは2〜3社からスモールスタートし、プレイブックの有効性やKPIの達成度を検証しましょう。
顧客からのフィードバックや活動データをもとに、支援内容やKPIを柔軟に見直し、改善を繰り返します。このプロセスを通じて、リスクを最小限に抑えながら、自社に最適なハイタッチの形を見つけ出すことができます。
ハイタッチ導入でよくある3つの失敗と回避策
ハイタッチ導入は、多くの企業が挑戦する一方で、残念ながら失敗に終わるケースも少なくありません。ここでは、先人の失敗から学び、自社での成功確率を高めるために、よくある3つの失敗パターンとその具体的な回避策を紹介します。
失敗1:KPIを設定せず「頑張っているだけ」で終わる
【失敗パターン】
CSMが顧客のために一生懸命に動き回り、顧客からの評判も良い。しかし、具体的なKPIが設定されていないため、その活動がどれだけ事業貢献に繋がっているのかを定量的に示すことができません。結果として、経営層から「コストセンター」と見なされ、予算削減の対象になったり、チームの士気が低下したりします。
【回避策】
導入ステップ1で解説した通り、必ず事業目標に連動したKPI(解約率、NRRなど)を設定します。そして、定期的にその進捗をモニタリングし、経営層や関連部署にレポートする仕組みを作りましょう。「我々の活動によって、重要顧客の解約率がX%改善しました」と具体的に示すことで、活動の価値を社内に証明し、継続的な協力や投資を得やすくなります。
失敗2:セグメント分けが曖昧でリソースが枯渇する
【失敗パターン】
「重要顧客」の定義が曖昧なまま、「困っている顧客は全員助けたい」という善意から対応範囲を広げすぎてしまいます。その結果、本来ハイタッチで対応すべきでない顧客にまで時間を費やしてしまい、CSMは常に多忙を極め、疲弊。本当に重要な顧客への対応品質が低下し、本末転倒な事態に陥ります。
【回避策】
導入ステップ2で解説したように、誰が見ても判断できる明確な基準でセグメントを定義し、「このセグメント以外にはハイタッチ対応は行わない」というルールを徹底します。冷たいように聞こえるかもしれませんが、これは限られたリソースを最も効果的に活用するための「選択と集中」です。これにより、持続可能な活動体制を築くことができます。
失敗3:支援が属人化し担当者不在で機能しなくなる
【失敗パターン】
特定の優秀なCSM(スーパーCSM)の個人的なスキルや経験に依存してしまい、その人がいないと顧客対応が回らなくなります。ナレッジが共有されず、組織としての知見が蓄積されないため、その担当者が退職・異動した途端にハイタッチ戦略全体が機能不全に陥ります。
【回避策】
導入ステップ3で解説したプレイブックの作成が最も有効な対策です。成功しているCSMのノウハウを形式知化し、チーム全体で共有できる仕組みを作りましょう。また、顧客情報や対応履歴をCRMやCSツールに記録し、誰でも過去の経緯を把握できるようにしておくことも重要です。これにより、支援の質を標準化し、組織的な対応力を高めることができます。
まとめ:ハイタッチで重要顧客との関係を深化させ事業成長を加速する
本記事では、カスタマーサクセスにおけるハイタッチ戦略について、その定義から具体的な導入ステップ、そしてよくある失敗の回避策までを網羅的に解説しました。
ハイタッチは、単なる手厚い顧客対応ではありません。適切な顧客を選び、戦略的にアプローチすることで、解約率の低下とLTVの最大化を実現し、事業全体の成長を加速させるための強力な「投資」です。その成功の鍵は、完璧な計画を待つことではなく、明確な目的意識のもと、まずは小さく始めて改善を繰り返すことにあります。
この記事で紹介した5つのステップを参考に、まずは「ステップ1:目的とKPIを明確にする」ことから始めてみてください。それが、貴社の重要顧客との関係を新たなステージへと引き上げ、持続的な成功を収めるための確かな第一歩となるはずです。