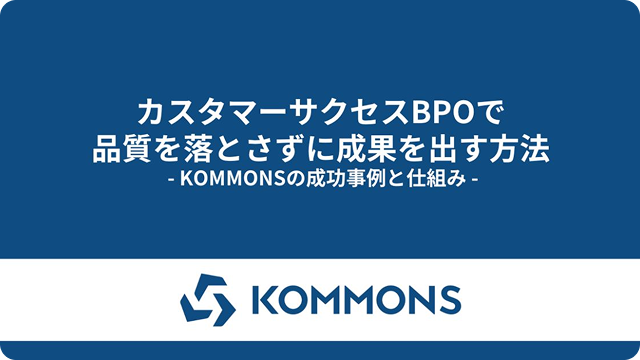2025.09.30
カスタマーサクセスのフレームワークとは?手探りの部門立ち上げから脱却する方法を解説
CSブログ
カスタマーサクセス部門の立ち上げを任されたものの、何から手をつければいいのか、具体的な進め方がわからず途方に暮れていませんか。
社内に手本となる経験者がおらず、自分の進め方が本当に正しいのか、暗闇の中を手探りで進んでいるような不安を感じることもあるのではないでしょうか。
多くの情報がある中で、自社に合ったカスタマーサクセスのフレームワークを見つけられないことも、つまずきの原因になりがちです。
この記事では、そんな手探りの状態から脱却し、自信を持って部門を推進するための実践的なロードマップを、具体的なフレームワークと共に解説します。
この記事の結論
- まず、顧客の成功を「オンボーディング完了」など具体的なフェーズに分解し、「サクセスロードマップ」を作成することから始めましょう。
- KPIは最初から完璧を目指さず、「オンボーディング完了率」など着手しやすい活動指標からスモールスタートすることが成功の鍵です。
- 顧客を契約金額などで分類し、まずは最重要顧客への「ハイタッチ」支援にリソースを集中させることが効果的です。
- 上司への説明には、フレームワークを使って「顧客の成功がLTV(顧客生涯価値)向上に繋がる」というロジックを視覚的に示しましょう。
- 全ての活動は、まずExcelやスプレッドシートで管理し、プロセスが固まってからツールの導入を検討するのが着実な進め方です。
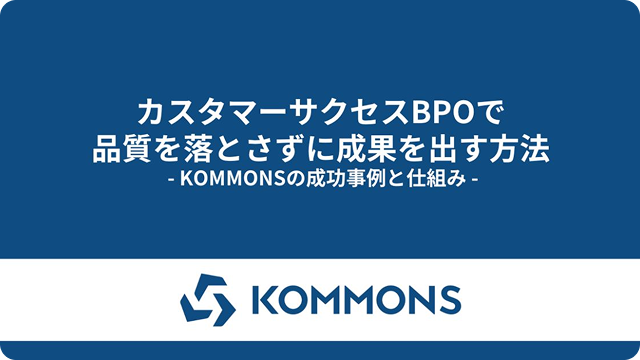
そもそもカスタマーサクセスにおけるフレームワークとは?
カスタマーサクセスにおけるフレームワークとは、顧客を成功に導き、自社の事業成長を実現するための一連の考え方や行動の「型」を指します。
単なる理論や概念図ではなく、複雑な課題を整理し、チーム全体で同じ方向を向いて進むための、極めて実践的なツールです。
部門の立ち上げという、まさに地図のない航海を始めるあなたにとって、このフレームワークは最も信頼できる武器となります。
フレームワークは部門立ち上げの「羅針盤」になる
カスタマーサクセス部門の立ち上げ期は、やるべきことが多岐にわたり、何から手をつけるべきか迷子になりがちです。
「顧客へのアプローチ方法は?」「活動の成果はどう測る?」「チームの役割分担は?」——次々と現れる問いに、一人で立ち向かうのは容易ではありません。
ここで役立つのが、カスタマーサクセスのフレームワークです。
フレームワークは、先人たちが試行錯誤の末に生み出した知恵の結晶であり、進むべき方向を示してくれる「羅針盤」の役割を果たします。
この羅針盤があれば、闇雲に進むのではなく、確かな指針を持って航海を進めることができるのです。
フレームワークを活用する3つのメリット
フレームワークを学ぶことには、具体的に3つの大きなメリットがあります。
これらは、あなた自身の業務効率化だけでなく、チームや経営層を巻き込む上でも強力な武器となります。
- 思考が整理され、優先順位が明確になる
やるべきことが明確な型に沿って整理されるため、何から着手すべきかという優先順位がつけやすくなります。これにより、場当たり的な対応から脱却し、戦略的な活動が可能になります。 - チームの「共通言語」が生まれる
「ヘルススコア」「タッチモデル」といったフレームワークの概念が、チーム内での共通言語になります。これにより、認識のズレがなくなり、円滑なコミュニケーションとスピーディーな意思決定が促進されます。 - 施策の抜け漏れを防ぎ、活動を体系化できる
顧客の成功までの道のりを体系的に捉えるため、「オンボーディングは手厚いが、その後のフォローが抜けていた」といった施策の抜け漏れを防ぐことができます。活動全体を俯瞰し、一貫性のあるアプローチを実現します。
カスタマーサクセス部門立ち上げの5ステップ
ここからは、カスタマーサクセスのフレームワークを具体的に活用し、部門を立ち上げるための実践的なロードマップを5つのステップで解説します。
このステップに沿って進めることで、手探りの状態から脱却し、着実に成果を出せる体制を構築できます。
ステップ1. 顧客の成功を定義する(カスタマージャーニーマップ)
カスタマーサクセスの活動は、すべて「顧客の成功」から始まります。
しかし、「成功」の定義は顧客によって様々です。
最初のステップは、あなたの会社の製品やサービスを使って顧客がどのような状態になれば「成功」と言えるのかを、具体的に定義することです。
ここで活用するのが「カスタマージャーニーマップ」というフレームワークです。
顧客が製品を認知し、契約し、利用を開始し、価値を実感して定着するまでの一連の体験を時系列で可視化します。
各フェーズで顧客が何を考え、何につまずき、何を達成したいのかを洗い出すことで、支援すべきポイントが明確になります。
ステップ2. 顧客の状態を可視化する(ヘルススコア)
顧客の成功を定義したら、次はその成功に向かって順調に進んでいるかを客観的に把握する必要があります。
勘や経験だけに頼るのではなく、データに基づいて顧客の状態を可視化するフレームワークが「ヘルススコア」です。
ヘルススコアは、顧客が製品やサービスを健全に利用しているかを示す健康診断のような指標です。
一般的に、以下の3つの要素を組み合わせて算出されます。
- 製品・サービスの利用状況:ログイン頻度、特定機能の利用率、アクティブユーザー数など
- サポートとの関係性:問い合わせ件数、満足度調査(NPSなど)の結果
- 契約・請求状況:ライセンスの利用率、アップセルの有無、支払い状況など
これらの要素に自社のビジネスモデルに合わせて重み付けを行い、スコアを算出します。
そして、「良好(緑)」「注意(黄)」「危険(赤)」のように色分けすることで、どの顧客に優先的にアプローチすべきかが一目でわかるようになります。
【コラム】ヘルススコア設計の第一歩:まずはExcelでシンプルに始める
「ヘルススコア」と聞くと、専門的なツールが必要で難しそうだと感じるかもしれません。
しかし、最初から完璧な仕組みを目指す必要はありません。
まずはExcelやスプレッドシートで、管理できる範囲の指標から始めてみましょう。
例えば、以下のようなシンプルな形で十分です。
- ログイン頻度:週3回以上なら「3点」、週1〜2回なら「2点」、週0回なら「1点」
- 主要機能の利用:利用していれば「2点」、していなければ「0点」
- サポートへのポジティブな声:あれば「1点」、なければ「0点」
このように各項目を点数化し、合計点で顧客の状態を判断します。
「合計5点以上は良好」「3〜4点は注意」「2点以下は危険」といったルールを決めるだけで、立派なヘルススコア管理の第一歩です。
運用しながら自社に合った指標や重み付けを見つけていくことが、成功への近道です。
ステップ3. 顧客に合わせたアプローチを設計する(タッチモデル)
全ての顧客に同じように手厚いサポートを提供するのは、リソースの観点から現実的ではありません。
そこで、顧客をいくつかのグループに分け、それぞれに最適なアプローチを行うためのフレームワークが「タッチモデル」です。
一般的に、顧客は契約金額や将来性などに応じて、以下の3つのセグメントに分類されます。
- ハイタッチ:最も重要な大口顧客。専任担当者がつき、定期的なミーティングや個別コンサルティングなど、手厚い支援を行います。
- ロータッチ:中規模の顧客層。担当者が複数社を兼任し、集合研修や定期的なメールマガジンなど、ある程度標準化された支援を行います。
- テックタッチ:小規模な顧客層。システムやテクノロジーを活用し、人間が介在しない形での支援が中心です。チュートリアル動画、FAQサイト、ステップメールなどでセルフオンボーディングを促します。
このタッチモデルに基づいてリソースを配分することで、効率的かつ効果的な顧客支援が可能になります。
ステップ4. 能動的な働きかけで成功へ導く(オンボーディング・DEARモデル)
顧客がサービスを契約した直後の初期体験は、その後の利用継続率を大きく左右する極めて重要な期間です。
この初期定着を支援するプロセスを「オンボーディング」と呼びます。
ここでは、顧客が「待っている」のではなく、こちらから能動的に働きかけ、成功体験へと導くことが重要です。
オンボーディングからその後の関係構築までを体系化した「DEARモデル」のようなフレームワークも参考になります。
- Deployment(導入):スムーズな利用開始を支援する。
- Engagement(関係構築):顧客との信頼関係を築く。
- Adoption(定着):製品・サービスの利用を習慣化させる。
- ROI(価値実感):投資対効果を顧客が実感できるように導く。
これらのステップを意識して働きかけることで、顧客の離脱(チャーン)を防ぎ、長期的な関係を築くことができます。
ステップ5. 活動の成果を測定し改善する(LTV・チャーンレート)
カスタマーサクセスは、単なる顧客満足活動ではありません。
事業の成長に直接貢献することを、数値で証明する必要があります。
そのための重要な指標が「LTV(顧客生涯価値)」と「チャーンレート(解約率)」です。
- LTV (Life Time Value):一人の顧客が、取引期間中に自社にもたらしてくれる利益の総額。
- チャーンレート (Churn Rate):一定期間内にサービスを解約した顧客の割合。
この2つは密接に関係しており、基本的なLTVは「平均顧客単価 ÷ チャーンレート」で算出できます。
つまり、チャーンレートを低減させることが、LTVの向上に直結するのです。
例えば、一般的にSaaSビジネスにおける月次チャーンレートは5%未満が健全な目安とされますが、これはあくまで参考値です。
自社のビジネスモデルに合わせて目標を設定し、CS活動がこれらの重要指標にどう貢献したかを測定・分析し、次の改善アクションに繋げていくことが不可欠です。
フレームワークを基にしたKPI設定と経営層への説明方法
部門を本格的に軌道に乗せるためには、活動の目標となるKPI(重要業績評価指標)を設定し、その重要性を経営層に理解してもらう必要があります。
ここが、多くの立ち上げ担当者が直面する大きな壁です。
フレームワークで整理した思考は、この壁を乗り越えるための強力な武器になります。
自社の事業フェーズに合ったKPIの選び方
KPIは、最初からLTVやチャーンレートといった最終的な成果指標だけを追うと、日々の活動との繋がりが見えにくくなります。
事業や部門のフェーズに合わせて、適切なKPIを選ぶことが重要です。
- 立ち上げ初期:まずは活動の量と質を測るKPIから始めましょう。例えば、「オンボーディング完了率」「ヘルススコアが良好な顧客の割合」「ハイタッチ顧客との月次ミーティング実施率」など、コントロールしやすい指標が適しています。
- 成長期:活動の成果が顧客の行動にどう繋がったかを測るKPIに移行します。「機能の利用率向上」「アップセル・クロスセルの件数」「顧客満足度(NPS)」などが挙げられます。
- 成熟期:最終的に事業貢献度を測るKPIを重視します。「チャーンレートの低減率」「LTVの向上額」「顧客単価の上昇率」など、経営インパクトの大きい指標を追います。
このように段階的にKPIを設定することで、チームの目標が明確になり、着実な成長を促すことができます。
上司を納得させるための報告・提案テンプレート
経営層に予算や人員を求める際、単に「顧客のために必要です」と訴えるだけでは不十分です。
カスタマーサクセス活動が、いかに事業成長に貢献するかを論理的に説明する必要があります。
そのためのストーリー構成は、以下のテンプレート要素を参考にしてください。
- 現状の課題提示(Problem)
「現在、月次チャーンレートがX%あり、年間でY円の損失に繋がっています。主な原因は、オンボーディングでのつまずきです。」 - 解決策の提案(Solution)
「そこで、オンボーディング専門チームを立ち上げ、ハイタッチでの支援を強化します。これにより、オンボーディング完了率をA%からB%へ引き上げます。」 - 期待される成果(Goal)
「オンボーディング完了率が向上することで、チャーンレートはZ%改善し、結果としてLTVが年間で〇〇円向上する見込みです。」 - 必要なリソース(Resource)
「この計画を実行するため、人員〇名と、活動管理のためのツール予算〇〇円が必要です。」
このように、課題から解決策、そして事業への貢献までを一本の線で繋げて説明することで、説得力が格段に増します。
まとめ:フレームワークを使いこなし、自信を持ってカスタマーサクセスを推進しよう
この記事では、カスタマーサクセス部門の立ち上げという大きな挑戦に臨むあなたのために、思考の整理から実践的なアクションまでを網羅したロードマップを解説しました。
最後に、ロードマップの要点を振り返ります。
- ステップ1:カスタマージャーニーマップで「顧客の成功」を定義する。
- ステップ2:ヘルススコアで「顧客の状態」を客観的に可視化する。
- ステップ3:タッチモデルで「顧客に合わせたアプローチ」を設計する。
- ステップ4:オンボーディングなどを通じて「能動的に成功へ」と導く。
- ステップ5:LTVやチャーンレートで「活動の成果」を測定し改善する。
カスタマーサクセスのフレームワークは、一度で完璧に使いこなす必要はありません。
まずはこのロードマップに沿って一歩を踏み出し、試行錯誤しながら自社に合った形に磨き上げていくことが何よりも重要です。
フレームワークという強力な羅針盤があれば、あなたはもう一人ではありません。
自信を持って、顧客の成功、そして事業の成長を力強く推進していきましょう。