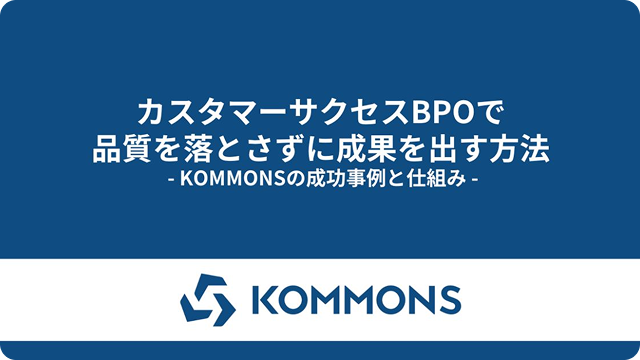2025.09.30
カスタマーサクセスにおけるチャーンとは?新任担当者向けに原因と改善の5ステップを解説
CSブログ
新しくカスタマーサクセス部門を任されたものの、何から手をつければ良いか分からず、途方に暮れていませんか。
「チャーンを改善するように」と指示されても、具体的な目標設定の根拠が見つからなかったり、社内に相談できる経験者がいなくて、自分の進め方が正しいのか不安になったりすることもあるかもしれません。
この記事は、そんなあなたのための伴走者です。
カスタマーサクセスにおけるチャーンの基本から、原因を特定するための考え方、そして明日から具体的に行動できる5つの改善ステップまで、新任担当者に必要な知識とアクションプランを一つのロードマップとしてまとめました。
この記事の結論
- カスタマーサクセスにおけるチャーンとは顧客の「解約」を指し、特にSaaSビジネスの成長を左右する最重要指標です。
- チャーンレートの目標設定では、まず業界平均(SaaSでは月次3%〜5%)を目安にし、自社の状況に合わせて現実的なKPIを立てましょう。
- 解約原因は主に「導入初期のつまずき」「価値を実感できていない」「サービス外の要因」の3つに分類して考えると、対策が立てやすくなります。
- 改善の第一歩として、データ分析の前にまず解約顧客へヒアリングを行い、課題の一次情報を集めることが最も効果的です。
- チャーン改善はCS部門だけで完結しません。分析結果を基に営業や開発など他部署を巻き込み、全社で取り組む体制を作ることが成功の鍵です。
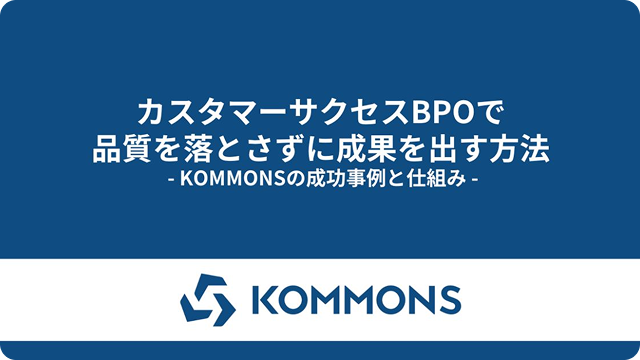
カスタマーサクセスにおけるチャーンとは?事業の成長を左右する重要指標
まずはじめに、基本となる言葉の定義から確認しましょう。
カスタマーサクセスにおける「チャーン(Churn)」とは、顧客が製品やサービスの利用を停止すること、つまり「解約」を意味します。
特に、SaaSのような月額課金制のサブスクリプションビジネスにおいて、チャーンは事業の健全性を測る「心拍数」に例えられるほど重要な指標です。
なぜなら、新しい顧客を獲得するコスト(CAC)は、既存顧客を維持するコストよりも一般的に高いからです。
せっかくコストをかけて獲得した顧客がすぐに解約してしまっては、事業は成長できません。
顧客に長くサービスを使い続けてもらい、顧客生涯価値(LTV)を最大化することこそが、安定した収益基盤を築く鍵となります。
そのため、チャーンをいかに低く抑えるかが、カスタマーサクセス部門の大きなミッションの一つとなるのです。
なお、チャーンには顧客数をベースにした「カスタマーチャーン」と、収益額をベースにした「レベニューチャーン」の2種類があり、両面から状況を把握することが大切です。
チャーンレートの計算方法と業界別の平均目安
チャーンの状況を客観的に把握し、改善目標を設定するためには「チャーンレート(解約率)」を算出する必要があります。
ここでは、基本的な計算方法と、上司や関係者に目標を説明する際に役立つ業界平均の目安をご紹介します。
基本的なチャーンレートの計算式
最も基本的なカスタマーチャーンレートは、以下の式で計算できます。
チャーンレート(%) = (期間中の解約顧客数 ÷ 期間開始時の総顧客数) × 100
例えば、ある月の初めに1,000社の顧客がいて、その月で20社が解約したとします。
その場合の月次チャーンレートは、以下のようになります。
(20社 ÷ 1,000社) × 100 = 2%
まずはこの計算式を使って、自社の現状を数値で把握することから始めてみましょう。
自社の目標設定に役立つ業界平均の目安
自社のチャーンレートを算出できたら、次はその数値が高いのか低いのか、判断する基準が欲しくなりますよね。
もちろん、ビジネスモデルや価格帯によって大きく異なりますが、一般的にBtoBのSaaS業界では、健全な月次チャーンレートの目安は3%〜5%程度とされています。
ある調査データ(Recurly Research)によれば、業界ごとの月次チャーンレートの中央値は、SaaS/ソフトウェア業界で約4.5%、教育業界では約6.1%という報告もあります。
また、顧客単価が低いビジネスほどチャーンレートは高くなる傾向があります。
これらの数値を参考にしつつも、まずは「月次3%」を最初の目標ラインとして設定し、そこから自社の状況に合わせて調整していくのが現実的なアプローチです。
この客観的なデータは、上司にKPIの目標値を説明する際の、説得力のある根拠としても役立つはずです。
顧客単価も考慮する「レベニューチャーン」とは?
顧客数ベースの「カスタマーチャーンレート」は分かりやすい指標ですが、一つ大きな弱点があります。
それは、「月額1万円の顧客1社の解約」も「月額100万円の顧客1社の解約」も、同じ「1社」としてカウントされてしまう点です。
事業へのインパクトは全く異なりますよね。
そこで重要になるのが、収益額ベースで解約率を測る「レベニューチャーンレート」です。
これは、失った収益が全体の何パーセントにあたるかを示す指標で、よりビジネスの実態に近い状況を把握できます。
さらに、既存顧客のアップセル(上位プランへの変更)やクロスセル(追加機能の購入)による収益増も考慮した「ネットレベニューチャーンレート」を追うことができれば、より高度な分析が可能です。
まずはカスタマーチャーンレートから始めるのが基本ですが、将来的にはレベニューチャーンも計測することで、より戦略的な意思決定ができるようになります。
チャーンレートが高くなる主な3つの原因
チャーンレートを改善するためには、まず「なぜ顧客は解約するのか」という根本原因を理解する必要があります。
原因は様々ですが、大きく分けると以下の3つのパターンに分類できます。
自社で起きているチャーンが、どのパターンに当てはまるか考えてみましょう。
原因1. オンボーディングが不十分で、価値を感じる前に離脱してしまう
これは、サービス導入後の最も早い段階で発生するチャーンです。
顧客は期待を持ってサービスを契約しますが、初期設定が複雑だったり、使い方が分からなかったりして、製品が提供する本来の価値を体験する前に「これは自分には合わないかもしれない」と感じてしまいます。
この「最初のつまずき」を放置してしまうと、顧客の利用意欲はどんどん低下し、あっという間に解約に至ってしまいます。
特に、導入初期のサポート体制が手薄な場合に起こりやすい問題です。
原因2. サービスを使いこなせず、成功体験を得られていない
オンボーディングの段階は乗り越えたものの、その後サービスを十分に活用しきれていないケースです。
ログインはしているけれど一部の基本的な機能しか使われていない、あるいは機能は使っているものの、それが顧客のビジネス成果に結びついていない状態を指します。
顧客がサービスに対する投資対効果(ROI)を実感できなければ、「このツールに毎月お金を払い続ける意味はあるのだろうか?」という疑問が生まれ、チャーンの危険信号が灯ります。
原因3. 価格や機能が顧客のニーズと合わなくなった
これは、製品そのものの問題というより、顧客を取り巻く外部環境の変化によって引き起こされるチャーンです。
例えば、以下のようなケースが考えられます。
- より安価で高機能な競合製品が登場した
- 顧客の事業方針が変わり、サービスが不要になった
- 会社の業績悪化により、予算が見直された
これらの要因はカスタマーサクセス部門だけでコントロールすることは困難です。
しかし、顧客との日々のコミュニケーションを通じて変化の兆候をいち早く察知し、営業部門や製品開発部門にフィードバックすることで、未然に防げるチャーンもあります。
新任担当者のためのチャーン改善ロードマップ5ステップ
チャーンの基本と原因を理解した上で、新任担当者のあなたが明日から具体的に何をどのような順番で進めていけば良いのか、5つのステップに分けて解説します。
このロードマップに沿って進めれば、手探りの状態から抜け出し、自信を持って改善活動を推進できるはずです。
ステップ1. まずは解約顧客へのヒアリングで一次情報を集める
チャーン改善と聞くと、すぐにデータ分析をイメージするかもしれませんが、その前にやるべき最も重要なことがあります。
それは、解約してしまった顧客に「なぜ解約したのか」を直接聞くことです。
データは「何が起きたか」を教えてくれますが、「なぜ起きたか」という背景や感情までは教えてくれません。
顧客の生の声にこそ、改善の最大のヒントが隠されています。
可能であれば電話で、難しければメールやアンケートフォームで、丁寧にお願いしてみましょう。
その際は、「サービスを良くするための参考にしたい」という姿勢で、以下のような質問を投げかけてみてください。
- 解約を決められた、一番の理由は何でしたか?
- サービスに最も満足していた点はどこでしたか?
- 逆に、最も不満だったり、使いにくいと感じたりした点はどこでしたか?
- もしサービスを使い続けるとしたら、どんな機能やサポートがあれば良かったですか?
ステップ2. 既存顧客の利用データから解約の予兆を見つける
ヒアリングで得られた顧客の声を仮説として、次にデータを見てみましょう。
解約した顧客と、現在も利用を継続している優良顧客のサービス利用状況を比較し、行動パターンの違いを探します。
これが「解約の予兆(シグナル)」を見つけるプロセスです。
見るべきデータは、例えば以下のようなものです。
- ログイン頻度(週に1回未満になっている、など)
- 主要機能の利用率(サービスの核となる機能が使われていない、など)
- サポートへの問い合わせ回数や内容(急に増えた、または全くなくなった、など)
- 管理者だけでなく、一般ユーザーの利用がアクティブか
最初は高度な分析ツールがなくても構いません。
まずはExcelなどを使い、手元にあるデータから比較を始めるだけでも、多くの発見があるはずです。
ステップ3. オンボーディングプログラムを見直し、最初の成功体験を最速で提供する
原因分析の結果、特に導入初期のチャーンが多いことが分かった場合、最優先で取り組むべきはオンボーディングの改善です。
顧客が契約後に初めてサービスに触れる体験は、その後の関係性を決定づける極めて重要な期間です。
いかに早く、顧客に「これなら自分でも使えそうだ」「この機能は便利だ!」という最初の成功体験(Ahaモーメント)を届けることができるかが鍵となります。
具体的な改善策としては、以下のようなものが考えられます。
- つまずきやすいポイントを解説する動画チュートリアルを用意する
- 契約後のウェルカムメールで、次に何をすべきか分かりやすく案内する
- 個別のキックオフミーティングや操作トレーニングを実施する
大きな仕組みを作る前に、まずは一つの顧客に徹底的に寄り添い、成功まで伴走してみることから始めるのも良いでしょう。
ステップ4. ヘルススコアを定義し、顧客の状態を可視化する
顧客数が増えてくると、全ての顧客の状況を感覚だけで把握するのは難しくなります。
そこで役立つのが、顧客の健全性を数値で可視化する「ヘルススコア」という考え方です。
これは、いわば「顧客の健康診断」のようなもの。
ステップ2で見つけた解約の予兆(ログイン頻度、機能利用率など)をいくつか組み合わせ、顧客ごとに点数をつけます。
例えば、「ログイン頻度が高い=5点」「主要機能を使っている=3点」のようにスコアリングし、合計点数が低い(=不健康な)顧客から優先的にアプローチする、といった判断ができるようになります。
最初から完璧なスコアを作る必要はありません。
まずは2〜3個のシンプルな指標から始めて、運用しながら精度を高めていきましょう。
これにより、属人的な顧客管理から、データに基づいた客観的な管理へと移行する第一歩を踏み出せます。
ステップ5. 営業や開発など他部署を巻き込み、全社で取り組む体制を作る
最後に、カスタマーサクセス部門だけでチャーン改善に取り組まない、ということです。
例えば、「受注時に過度な期待をさせてしまい、導入後にギャップが生まれる」のは営業部門との連携が必要ですし、「顧客が求める機能が不足している」のであれば製品開発部門との協力が不可欠です。
あなたがヒアリングやデータ分析で得た「顧客の声」は、他部署にとっても非常に価値のある情報です。
「〇〇という理由で解約したお客様が、今月3件ありました。この傾向は受注時のご提案で防げるかもしれません」といったように、客観的なデータとして定期的に共有する場を設けましょう。
チャーンは全社の課題であるという認識を広げ、仲間を作っていくこと。
それが、新任担当者のあなたがプロジェクトを成功に導くための、何よりの力になります。
まとめ|チャーン改善の第一歩は顧客を深く知ることから
今回は、カスタマーサクセスにおけるチャーンの基本から、具体的な改善ロードマップまでを解説しました。
チャーンレートの改善は、一朝一夕で成し遂げられる簡単な課題ではありません。
しかし、本記事でご紹介したように、正しいステップを踏めば、必ず成果に繋がります。
様々な分析手法やテクニックがありますが、その根底にある最も大切なことは、たった一つです。
それは、「顧客を深く知ろうとする姿勢」です。
データやスコアの向こう側にいる、一人ひとりの顧客が何に悩み、何を成し遂げたいのかに真摯に耳を傾けること。
その積み重ねが、顧客との信頼関係を築き、結果としてチャーンの低下に繋がっていきます。
完璧な計画を立てるのを待つ必要はありません。
まずはロードマップのステップ1、「一人の解約顧客に話を聞いてみること」から、今日、始めてみませんか。
あなたのその一歩が、事業を大きく成長させるきっかけになるはずです。