2025.08.12
カスタマーサクセスの立ち上げ方を5ステップで解説!失敗しない進め方と組織づくりのコツ
CSブログ
「会社からカスタマーサクセスを立ち上げろと言われたけど、何から手をつければいいの?」「専任担当者もいないのに、通常業務と兼務でどうやって進めればいいんだろう…」
サブスクリプション型ビジネスの普及に伴い、カスタマーサクセスの重要性はますます高まっています。しかし、その重要性は理解できても、いざ「立ち上げ担当者」になると、具体的な進め方やリソースの確保、成果の測り方など、見えない壁にぶつかり、途方に暮れてしまう方は少なくありません。
ネットで成功事例を調べても、自社の状況とはかけ離れていて、現実的な第一歩が踏み出せずにいるのではないでしょうか。
本記事では、以下のような課題を解決します:
- 何から始めるべきかが分かる、具体的な立ち上げの手順
- 専任担当者や十分な予算がなくても始められる、現実的な進め方
- 上司や経営層に活動の成果を説明するための、重要なKPIとその使い方
- 営業や開発など、他部署を巻き込み、協力体制を築くための交渉のヒント
- 多くの人が陥りがちな失敗パターンとその乗り越え方
この記事では上記のような課題を持っている方に向けて、カスタマーサクセスの立ち上げ方を、担当者1人からでも始められる5つのステップで詳しく解説します。この記事を参考にすれば、明日から何をすべきかが明確になり、自信を持ってカスタマーサクセスの成功に向けた第一歩を踏み出すことができるでしょう。
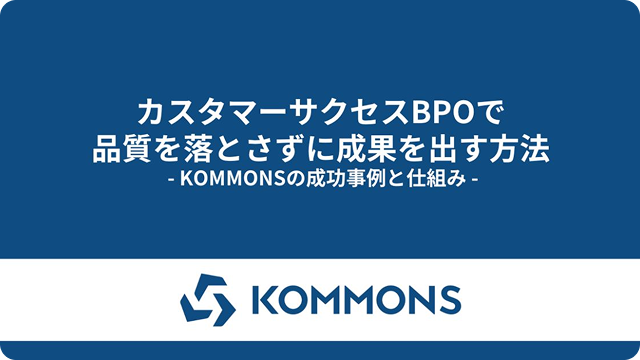
なぜ今、カスタマーサクセスの立ち上げが重要なのか
カスタマーサクセスの立ち上げを検討する際、まず初めに押さえるべきは「なぜ、それが必要なのか」という目的です。この目的が明確でなければ、社内の協力を得ることも、活動を継続することも難しくなります。ここでは、事業成長に直結する3つの重要な理由を解説します。これらは、経営層や他部署を説得する際の強力な論拠となるはずです。
LTVを最大化し、安定した収益基盤を築くため
LTV(Life Time Value:顧客生涯価値)とは、一人の顧客が取引を開始してから終了するまでの期間にもたらす利益の総額を指します。特に、月額課金などのサブスクリプションモデルでは、新規顧客の獲得コスト(CAC)を回収し、利益を生み出すためには、顧客に長期間サービスを使い続けてもらうことが不可欠です。
カスタマーサクセスは、顧客が製品・サービスを最大限に活用し、成功体験を得られるよう能動的に支援することで、顧客満足度と定着率を高め、LTVの最大化に直接貢献します。これは、事業の安定した収益基盤を築く上で最も重要な活動です。
解約率を改善し、事業成長を加速させるため
SaaSビジネスにおいて、解約率(チャーンレート)は事業の成長を阻害する最大の要因の一つです。たとえ新規顧客を順調に獲得できていても、高い解約率が続けば、収益は伸び悩み、やがて成長は頭打ちになります。
カスタマーサクセスは、顧客の利用状況をデータで把握し、解約の兆候を早期に察知してプロアクティブ(能動的)な働きかけを行います。問題が発生してから対応する「カスタマーサポート」とは異なり、問題が起こる前に手を打つことで、解約を未然に防ぎ、事業の成長を加速させることができるのです。
顧客の声を製品・サービス改善に活かすため
カスタマーサクセス部門は、日々顧客と最も近い距離で接するため、製品・サービスに対するリアルなフィードバックや要望の宝庫です。
これらの「顧客の声」は、単なるクレーム処理で終わらせるべきではありません。カスタマーサクセスがハブとなり、顧客から得た貴重なインサイトを開発部門やマーケティング部門にフィードバックすることで、より顧客ニーズに合った製品改善や、効果的なマーケティング施策に繋げることができます。全社で顧客中心の文化を醸成し、市場での競争優位性を高める上で、カスタマーサクセスは不可欠な役割を担います。
カスタマーサクセス立ち上げの具体的な5ステップ
「重要性は分かったけれど、具体的に何から始めればいいのか…」ここからは、そんな疑問にお答えします。カスタマーサクセスの立ち上げは、壮大な計画を立てるよりも、実行可能な小さなステップに分解して進めることが成功の鍵です。ここでは、担当者1人からでも始められる、具体的な進め方を5つのステップで解説します。
1. 目的とゴールの設定(KGI・KPIの明確化)
まず最初に、「何のためにカスタマーサクセスを行うのか」という目的(KGI:重要目標達成指標)を明確に定義します。例えば、「年間解約率を10%から5%に低減する」「LTVを前年比で20%向上させる」など、具体的で測定可能なゴールを設定しましょう。
そして、そのKGIを達成するための中間指標としてKPI(重要業績評価指標)を設定します。例えば、「オンボーディング完了率」「ヘルススコア」「アップセル・クロスセル件数」などが挙げられます。
この目的とゴールが、今後の活動の方向性を決める羅針盤となります。
2. 顧客の定義とセグメント分け
次に、「誰の成功を支援するのか」を明確にします。すべての顧客に同じように手厚いサポートを提供するのは、特にリソースが限られた状況では不可能です。
そこで、顧客をいくつかのセグメント(グループ)に分類します。例えば、契約金額や利用状況、今後の成長ポテンシャルなどに応じて、「ハイタッチ(手厚い個別対応)」「ロータッチ(セミナーや勉強会など、1対多の対応)」「テックタッチ(FAQやチュートリアル動画など、テクノロジーを活用した対応)」といったように、提供するサポートのレベルを分けます。
立ち上げ初期は、最も成功させたい優良顧客層に絞ってハイタッチから始めるのが現実的です。
3. オンボーディングプロセスの設計
オンボーディングとは、顧客が製品・サービスを契約してから、基本的な操作を習得し、価値を実感できるようになるまでの初期プロセスです。
この期間の体験が、その後の利用継続率を大きく左右します。顧客が「つまずきやすいポイント」はどこか、どうすれば「最初の成功体験(Aha!モーメント)」を早期に提供できるかを考え、具体的な支援プロセスを設計しましょう。
例えば、「キックオフミーティング」「初期設定サポート」「目標設定ワークショップ」などを体系的に提供することで、顧客の離脱を防ぎ、スムーズな活用を促進します。
4. ヘルススコアの定義と運用の開始
ヘルススコアとは、顧客が製品・サービスを健全に利用できているかを示す「健康診断」のような指標です。サービスのログイン頻度、主要機能の利用率、サポートへの問い合わせ回数など、複数のデータを組み合わせてスコア化します。
このヘルススコアを定義し、定期的にモニタリングすることで、解約の危険性が高まっている顧客を早期に発見し、プロアクティブなアプローチが可能になります。最初はExcelなどで手動管理から始めても構いません。勘や経験に頼らない、データに基づいたカスタマーサクセス活動の第一歩です。
ヘルススコアは完璧でなくてOK!まずは仮説から始めよう
ヘルススコアを定義しようとすると、「どの指標が本当に解約と相関するのか分からない」と悩んでしまいがちです。しかし、最初から完璧なスコアを作る必要はありません。まずは「おそらく、この機能を使っている顧客は定着しやすいだろう」「ログイン頻度が高い顧客は満足度が高いはずだ」といった仮説ベースで、3〜5個程度のシンプルな指標から始めてみましょう。
重要なのは、運用しながらデータを蓄積し、「実際にヘルススコアが低かった顧客は解約率が高かったか?」を検証し、定期的にスコアの定義を見直していくことです。スモールスタートで始め、改善を繰り返すことが成功への近道です。
5. 運用と改善のサイクルを回す
ステップ1〜4で設計した施策を実行したら、必ずその効果を測定し、改善のサイクル(PDCAサイクル)を回します。
設定したKPIは計画通りに推移しているか、実施した施策は顧客のヘルススコア改善に繋がったかなどを定期的に振り返りましょう。
顧客からのフィードバックを積極的に収集し、オンボーディングプロセスやサポート内容を継続的に見直すことが重要です。カスタマーサクセスは一度作って終わりではなく、顧客と共に育てていく活動なのです。
立ち上げを成功させる組織づくりと重要KPI
具体的なステップが見えてきても、「担当者は自分一人だけ…」「活動の成果をどうやって上司に報告すればいいの?」といった組織や評価に関する悩みは尽きません。
ここでは、カスタマーサクセスの立ち上げを成功に導くための、現実的な組織体制の作り方、必ず押さえるべき重要KPI、そして社内を巻き込むためのヒントを解説します。
担当者1人・兼務から始める現実的な組織体制
理想を言えば専任チームを立ち上げたいところですが、多くの企業では担当者1人、あるいは他業務との兼務からスタートするのが現実です。
リソースが限られているからこそ、「やること」と「やらないこと」を明確にすることが重要です。まずは前述の顧客セグメントに基づき、対応する顧客を「上位20%のハイタッチ顧客」に限定しましょう。そして、すべての課題を一度に解決しようとせず、「オンボーディングの完遂」など、最もインパクトの大きい業務にフォーカスします。
既存の営業資料やFAQをコンテンツとして再活用するなど、ゼロから作らない工夫も大切です。
必ず押さえるべき4つの重要KPI
活動の成果を客観的に示し、社内の理解を得るためには、データに基づいた報告が不可欠です。以下の4つのKPIは、カスタマーサクセスの成果を測る上で特に重要です。これらを定点観測し、上司や経営層に報告するための武器としましょう。
- ヘルススコア: 顧客のサービス利用状況をスコア化した先行指標。解約の兆候を事前に察知するために使います。
- 解約率(チャーンレート): 特定期間内に失われた顧客や収益の割合を示す遅行指標。ビジネスの安定性を示す最重要指標の一つです。顧客数ベースの「カスタマーチャーン」と、収益ベースの「レベニューチャーン」の両方を見ると、より正確な状況が把握できます。
- NRR(Net Revenue Retention / 売上継続率): 既存顧客からの売上が、アップセルやクロスセルによって前年同月比でどれだけ増減したかを示す指標。計算式は「(当月のMRR + アップセルMRR – ダウンセルMRR – 解約MRR)÷ 前年同月のMRR × 100」です。NRRが100%を超えると、既存顧客だけで事業が成長していることを意味し、SaaSビジネスの健全性を示す鍵となります。
- LTV(顧客生涯価値): 顧客が取引期間中にもたらす利益の総額。CS活動が最終的に事業収益にどれだけ貢献しているかを示す指標です。
他部署(特に営業・開発)を巻き込むための交渉術
カスタマーサクセスは、単独の部署で完結する活動ではありません。特に、顧客獲得を担う「営業」と、製品を開発する「開発」との連携は不可欠です。
しかし、他部署はそれぞれの目標(KPI)を追っているため、協力を得るには工夫が必要です。重要なのは、相手のメリットを提示し、Win-Winの関係を築くことです。
- 対 営業部門: 「CSが既存顧客の満足度を高めれば、成功事例が生まれて新規営業の強力な武器になります」「アップセルの機会を創出し、営業部門の売上目標達成に貢献します」といった形で、営業のKPI達成にどう貢献できるかを具体的に伝えましょう。
- 対 開発部門: 顧客から得た具体的なフィードバックを「〇〇機能のUIが分かりにくいため、オンボーディングで3割の顧客が離脱しかけている」といったように、データと共に提供します。これにより、開発チームは改善の優先順位をつけやすくなり、開発工数の無駄を減らせます。
ここでつまずく!立ち上げ時によくある失敗と乗り越え方
新しい取り組みには失敗がつきものです。「失敗したくない」と不安に思うのは、あなただけではありません。ここでは、多くの担当者が立ち上げ時につまずきがちな3つの失敗例と、それを乗り越えるための具体的な対策を解説します。事前に知っておくことで、同じ轍を踏むのを防ぎましょう。
失敗例1:目的が曖昧なまま見切り発車してしまう
「とにかく何か始めなければ」という焦りから、目的やゴール設定が曖昧なまま活動をスタートさせてしまうケースです。これでは、施策の優先順位がつけられず、活動が場当たり的になります。
さらに、成果を客観的に示すことができないため、やがて「カスタマーサクセスって、何をやっているか分からない」と社内で評価されなくなり、協力を失ってしまいます。
【乗り越え方】
必ず立ち上げのステップ1に戻り、経営層や関連部署を巻き込んで「カスタマーサクセスで何を達成したいのか(KGI)」について合意形成を行いましょう。最初は「解約率の改善」など、シンプルで分かりやすい目標を一つに絞ることが重要です。
失敗例2:いきなり完璧な体制やツールを目指してしまう
「最高のカスタマーサクセスを実現するぞ!」と意気込むあまり、最初から完璧な組織体制や高機能な専門ツールの導入を目指してしまうパターンです。
しかし、リソースやノウハウが不足している立ち上げ期に完璧を求めると、計画倒れになったり、導入したツールを使いこなせずにコストだけがかさむ結果に陥りがちです。これは、情報処理推進機構(IPA)の「DX白書」などでも指摘されている、多くの企業が陥るIT投資の課題でもあります。
【乗り越え方】
完璧主義を捨て、「スモールスタート」と「段階的な拡張」を徹底しましょう。まずはExcelやスプレッドシートでの顧客管理から始め、手動でヘルススコアを計測してみる。その中で課題が見えてきて、「この作業を自動化したい」という具体的なニーズが生まれてから、ツールの導入を検討するのが賢明です。
失敗例3:成果を可視化できず、社内の協力を失う
日々の顧客対応に追われ、活動の成果を記録・報告することを後回しにしてしまうケースです。どんなに顧客のために尽くしていても、その努力と成果が可視化されなければ、社内での評価には繋がりません。
結果として、「コストセンター」と見なされ、予算や人員の追加を得られず、活動が尻すぼみになってしまいます。
【乗り越え方】
定期的な活動報告を仕組み化しましょう。週次や月次で、設定したKPI(ヘルススコアの推移、オンボーディング完了数など)の状況をまとめ、関係者に共有します。大きな成果だけでなく、「A社の〇〇様から感謝の言葉をいただいた」「この施策で、ヘルススコアが赤だった顧客が黄色に改善した」といった小さな成功(Quick Win)を積極的にアピールすることも、社内の雰囲気を良くし、協力者を増やす上で非常に効果的です。
まとめ:まずは顧客を1社サクセスさせることから始めよう
本記事では、カスタマーサクセスの立ち上げ方を、その重要性から具体的な5つのステップ、組織づくり、そしてよくある失敗例まで網羅的に解説しました。
改めて、重要なポイントを振り返ります。
- 目的の明確化: なぜCSをやるのか(LTV向上、解約率低減)を明確にする。
- 5つのステップ: ①目的設定 → ②顧客定義 → ③オンボーディング設計 → ④ヘルススコア定義 → ⑤改善サイクルの順で進める。
- スモールスタート: 完璧を目指さず、担当者1人、顧客数社からでも始められることから着手する。
- KPIによる可視化: ヘルススコア、解約率、NRR、LTVなどの指標で成果を客観的に示す。
- 社内の巻き込み: 他部署のメリットを提示し、Win-Winの関係を築く。
情報量が多く、やるべきことがたくさんあるように感じたかもしれません。しかし、最も大切なのは、完璧な計画を立てることよりも、まず行動を起こすことです。壮大な計画は一旦脇に置き、まずはあなたの会社にとって最も重要な顧客を1社選び、その顧客を徹底的にサクセスさせることだけに集中してみてはいかがでしょうか。
その1社の成功体験が、あなたにとっての自信となり、社内を説得する最高の事例となり、次のステップに進むための大きな原動力となるはずです。この記事が、あなたの挑戦の背中を押し、成功への第一歩を踏み出す一助となれば幸いです。